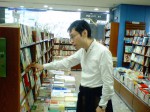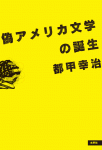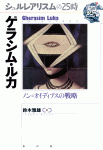編集部通信/『文芸時評』
2010年 4月 5日
すでにご存じのかたも多いと思いますが、
毎月1回、毎日新聞紙上に掲載されていた
川村湊さんの文芸時評が、この3月をもって17年間で終了しました。
川村さん、本当にお疲れさまでした。
文芸時評を長期にわたって継続して書くという作業は、
それはもう労ばかり多くして報われることの少ない仕事です。
ある作品のネガティヴな側面について一度でもふれようものなら
そのさきずっと作者から憎まれもするでしょうし、かといっておべんちゃらばかりでは
ことばが読者に届きません。文芸評論家としての能力がもっとも問われる、
その地道な仕事を、川村さんが17年間にわたって持続させてきた
という事実は、もっともっと評価されてしかるべきでしょうし、
文学史の記録にも記憶にも残る、といっても過言ではないと思います。
その川村さんの仕事の15年分を一挙に収録したのが、
2008年7月に弊社から刊行された『文芸時評 1993-2007』。
A5判上製9ポ2段組636ページの大冊です。
刊行時には富岡幸一郎さんから「これこそが現代文学史」と評価され、
現在も東京新聞で時評を担当している沼野充義さんからも
ご高評をいただきました(*)。
いわゆるポスト冷戦の開始とときを同じくして始まり、
阪神淡路大震災、オウム真理教事件を経て、
いまだ混沌としている21世紀に突入して現在にいたる《文学》と
それをめぐるさまざまな状況を《定点観測》した貴重な証言です。
ぜひこの機会に手にとってみてください。
ちなみに今月からは気鋭の評論家、田中和生さんが引き継ぐそうです。
その川村さんと田中さんの新旧対談はこちら(*)。
これからの新しい紙面も楽しみにしたいと思います。(編集部 Naovalis)
—
 川村 湊
川村 湊
『文芸時評 1993-2007』
A5判上製636頁/定価5000円+税ISBN978-4-89176-682-5 C0095
松浦寿輝氏推薦!
日本の小説界の空気と風土が激変したこの15年、
川村湊は一つところにじっと腰を据え、
気温の変化を肌で感じ、日差しと翳りの推移に目を凝らし、
何もかもを視野に収め、肩に力を入れない自然体で、
平静に、平明に、寛大に、辛辣に、「いま何が起きているか」を証言し続けてきた。
「持続とは力なり」という言葉を、これほど鮮やかに示している仕事もないと思う。