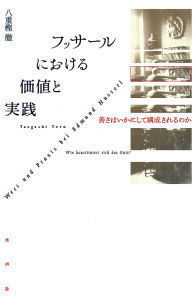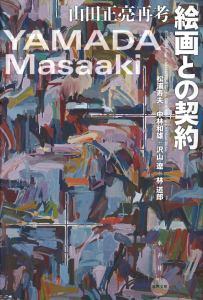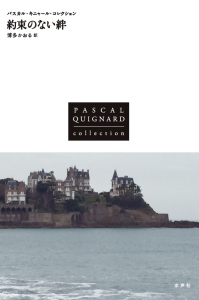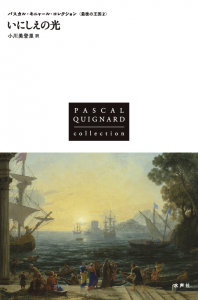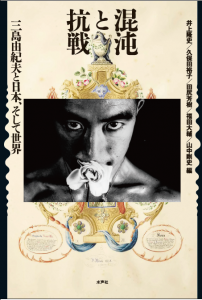2016年 12月 13日
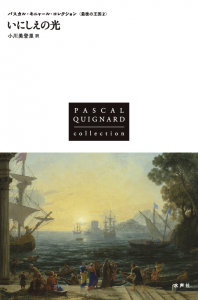
いにしえの光〈最後の王国2〉
《パスカル・キニャール・コレクション》
小川美登里(訳)
判型:四六判上製
頁数:336頁
定価:3000円+税
ISBN:978-4-8010-0221-0 C0397
好評発売中!
異時間の恍惚
時間に論理性はない――
ナチス以後、また原爆投下以後の、「人間性の終焉」の時代に、滅びることなくいきいきと甦る古代壁画。無情の時間の流れの彼方にある性の輝きを探究する、ベルグソンを専攻していた著者ならではの「時間」論。
【
訳者について】
小川美登里(おがわみどり)
1967年、岐阜県に生まれる。筑波大学人文社会系准教授(専攻、フランス現代文学)。ジェンダー、音楽、絵画、文学などにも関心をもつ。主な著書に、La Musique dans l’œuvre littéraire de Marguerite Duras(L’Harmattan, 2002)、Voix, musique, altérité : Duras, Quignard, Butor(L’Harmattan, 2010) 、Midori OGAWA & Christian DOUMET(dir.), Pascal Quignard, La littérature à son Orient(Presses Universitaires de Vincennes, 2015)、Dictionnaire sauvage, Pascal Quignard(collectif, Herman, 2016)などがある。
【
パスカル・キニャール・コレクション】
一覧のページは
こちらです。
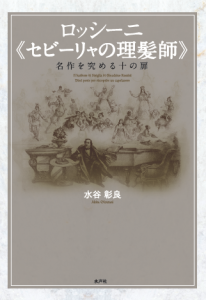 ロッシーニ《セビーリャの理髪師》
ロッシーニ《セビーリャの理髪師》